日本企業にはDX推進を阻む7つの課題があります。これらとは別に、DX推進に携わる部署ごとに、異なる課題を抱えてもいます。本記事ではDX推進を阻むこれらの課題とその解決策を詳しく解説。日本におけるDXの現状や、DXの3つの種類も紹介します。
目次
1. 日本におけるDXの現状
日本におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)は、政府の強力な推進もあり、あらゆる業界で取り組みが加速しています。
しかし、その進捗状況は企業によって大きく異なります。成功事例もあれば、課題に直面している企業も多いのが現状です。
「日本企業のDX推進実態調査2023~未来を創る全社DXへの挑戦~」によると、DX推進に成功している企業はわずか11.8%に留まっており、多くの企業がDXの推進に苦戦していることが浮き彫りになっています。
DXを推進するうえで特に大きな障壁となるのが、DX人材の不足、ITリテラシーの不足、レガシーシステムの存在などです。また、DXの目的や目標が曖昧なまま取り組みを進めてしまい、期待した成果を得られないケースも見られます。
2. 日本企業のDX推進を阻む7つの課題と解決策
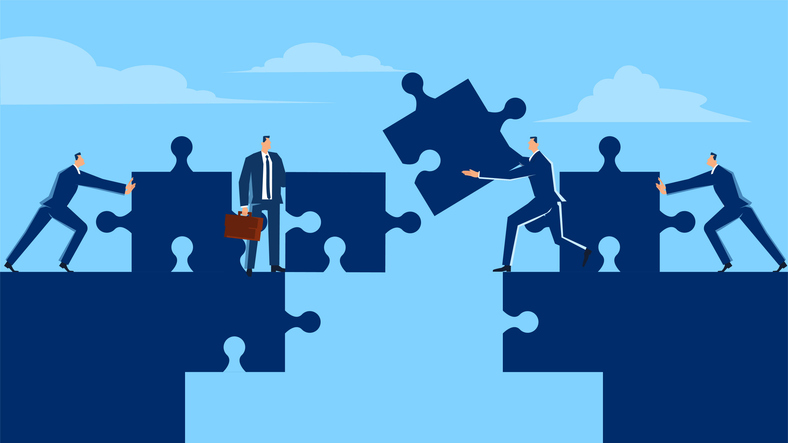
DXの重要性が叫ばれる一方で、日本企業はDX推進においてさまざまな課題に直面しています。ここでは、日本企業のDX推進を阻む7つの課題と、それぞれの解決策について詳しく解説していきます。
2-1. DX人材の不足
DXを推進するためには、最低でもIT技術に精通していなければなりません。それだけでなく、ビジネスの課題を理解し、デジタル技術を駆使して解決策を導き出せることも必要です。
具体的には、以下のようなスキルを持つ人材が求められます。
- ビジネス課題の分析力
- データ分析力
- IT技術に関する知識
- プロジェクトマネジメント能力
- コミュニケーション能力
- リーダーシップ
これらのスキルを兼ね備えた人材は、育成にも時間がかかるため、外部からの獲得も容易ではありません。日本ではこのようなDX人材が不足しており、多くの企業にとってDX推進の障壁となっています。
【解決策】
DX人材の不足を解決するためには、社内での人材育成と並行して、外部人材の活用も検討する必要があります。
まずは研修制度の導入やOJTによる育成などを通して、既存社員のスキルアップを図りましょう。副業や兼業を認めることで、社外からDX人材を獲得する手段もあります。
即戦力となるDX人材を外部から採用するには、コンサルティング会社やITベンダーにDX推進を支援してもらうなどの方法も有効です。
これらと並行して業務プロセスを効率化し、少ない人数でもDXを推進できる体制を構築することも重要です。
2-2. ITリテラシーの不足
DXを推進するためには、従業員一人ひとりがITツールやデジタル技術を理解し、活用できなければなりません。しかし日本企業では、従業員のITリテラシーが不足しているといわれています。
ITリテラシーとは、IT機器やソフトウェアを操作する能力だけを指すのではありません。情報の収集や分析、発信、コミュニケーションなど、デジタル社会で必要とされる幅広い知識やスキルを指します。
ITリテラシーが不足すると、新しいシステムやツールを導入しても使いこなせません。これでは、DXの効果を十分に発揮することもできないでしょう。
【解決策】
ITリテラシー不足を解消するためには、継続的な教育と、ITツールを活用しやすい環境づくりが重要です。
まずは社員向けのITリテラシー研修を定期的に実施し、基本的なITスキルから学ばせるのがいいでしょう。そのうえで、データ分析やセキュリティ対策など、DXに必要な知識を習得させます。
そのために役立つのがeラーニングです。eラーニングシステムを導入することで、社員一人ひとりのレベルに合わせた学習機会を提供できます。また、スキマ時間を学習に充てやすくなる、進捗管理がしやすくなり管理コストを削減できるといったメリットもあります。
ITリテラシーの高い社員が中心となり、質問や相談ができる社内コミュニティを設立するのも有効です。
そして、従業員の学習を進めながら、ITツールを活用しやすい環境を整えましょう。座学で身に着けた知識を血肉するためには、実践が一番だからです。
2-3. DXに対する誤解
DXに対する誤解も、推進を阻む大きな要因です。よくある誤解として、「DX=業務効率化」という考え方があります。たしかにDXは業務効率化に貢献しますが、それはあくまで手段のひとつに過ぎません。
DXの本質は、デジタル技術を活用してビジネスモデルを変革することです。業務効率化にとらわれすぎると、DXの本来の目的を見失い、真の変革を達成することが難しくなります。
その反対に、DXを壮大にとらえすぎるのも問題です。「DXには大規模なシステム導入やビジネスモデルの抜本的な改革が必要で、多大な費用と時間が必要になる」と思い、腰が重くなり着手できないケースもあります。
【解決策】
DXに対する誤解を解き、正しい理解を浸透させるためには、社内で共通認識を持つことが重要です。そのうえで、社内外におけるDXの成功事例や失敗事例を共有することで、DXに対する理解を深められます。
DXを、最初から大規模な取り組みとして始めてはいけません。まずはちょっとした業務効率化のような、小規模なプロジェクトから始めましょう。小さな成功体験を積み重ねることで、社員の意識を改革していくことが重要です。
2-4. DXの目的化
DXを推進する目的は、あくまでも企業の競争力強化や新たな価値創造です。DXはそのための手段に過ぎません。
しかし、「とりあえずDXを推進しよう」というように、DX自体が目的にすり替わってしまうケースも見られます。このような「DXの目的化」は、DX推進を阻害する大きな要因となります。
【解決策】
DXを推進する際には、まず「なぜDXが必要なのか」「DXによって何を実現したいのか」という目的を明確にしましょう。目的が曖昧なままDXを推進しても、期待した成果を得ることはできません。
成功しないのは、たとえばただ単にAIを導入すれば良い、最新のシステムを導入すれば良いというような考え方です。AIやシステムは、あくまで課題解決のためのツールです。これらをどのように活用して、どのような成果を上げるのかを明確にする必要があります。
2-5. システムのレガシー化
長年使い続けているシステムは老朽化し、最新の技術に対応できないケースがあります。このようなシステムは「レガシーシステム」と呼ばれ、DX推進の大きな足かせとなります。
レガシーシステムの問題点として、まず挙げられるのがブラックボックス化です。これは、開発担当者が退職するなどして、システムの仕様や構造がわからなくなっている状態を指します。ブラックボックス化してしまうと、システムの改修や連携が困難になり、DX推進の妨げとなります。
また、古いシステムは維持管理に多大なコストがかかります。その結果、DXに投資できる資金が限られてしまい、DX推進が遅れてしまうかもしれません。データの連携や活用が難しいことも多く、DXに欠かせないデータドリブンな経営の妨げとなる可能性もあります。
【解決策】
レガシーシステムの問題を解決するためには、いくつかの対策が考えられます。
ひとつは、最新の技術に対応したシステムに刷新する方法です。初期費用は大きくなりますが、長期的な視点で見れば、維持管理コストの削減やセキュリティリスクの低減につながります。
また、既存のシステムを活かしながら、段階的に最新技術を導入していく方法もあります。システム刷新に比べて、費用を抑えながら、段階的にシステムを改善していけます。
システムをクラウド型に移行するのもいいでしょう。クラウド型のシステムはベンダーが保守・運用するため、維持管理の負担を軽減しながら拡張性を向上させられます。
2-6. 攻めのIT投資に消極的
多くの日本企業は「攻めのIT投資」に消極的です。攻めのIT投資とは、ビジネスモデルの変革を目的にIT技術に投資することで、まさにDXのための投資といえます。
日本では業務効率化やコスト削減などを目的とした「守りのIT投資」に力を入れる企業が多いです。業務効率化もDXのプロセスのひとつであり、コスト削減によりDX推進の予算を確保できるかもしれませんが、DX推進を阻む土壌となっているのはたしかです。
【解決策】
攻めのIT投資を促進するためには、DXによって得られる効果を定量的に示す必要があります。たとえば、新規事業創出による収益増加、既存事業に新たな価値を付加することでLTVがどの程度上がるのかなどです。
そのために、IT投資の評価制度も見直しましょう。短期的な費用対効果だけでなく、中長期的な視点でIT投資を評価できるような制度を導入することが求められます。また、最初から多額の投資を行うのではなく、段階的に投資を行い、効果を検証しながら進めていく方法も有効です。
2-7. ボトムアップ型のすり合わせ文化
日本企業には、関係部署との調整や合意形成を重視するボトムアップ型の意思決定文化が根強く残っています。ボトムアップ型のメリットは、慎重な意思決定や現場を踏まえた改革などを可能にすることです。
その一方で、DX推進においてはスピード感が欠如し、変化への対応の遅れにつながる恐れがあります。
変化の激しいデジタル時代において、DX推進では迅速な意思決定と行動が求められます。しかし、関係部署との調整に時間をかけすぎたり、合意形成を優先するあまり大胆な改革に着手できなかったりするケースが見られます。
【解決策】
DX推進においては、トップダウン型の意思決定を導入しましょう。これにより、迅速な意思決定と行動が可能になります。また、現場に権限を委譲し、迅速な意思決定を促すことも重要です。
失敗を恐れず、変化に挑戦する文化を醸成することで、DX推進を加速させられます。DXを成功させるためには、従来の文化にとらわれず、変化に対応できる柔軟な組織体制を構築しましょう。
3. 部門別のDX推進を阻む課題と取り組むべきこと

DX推進は全社的な取り組みですが、部門ごとに異なる課題が存在します。それぞれの部門が抱える課題を理解し、適切な対策を講じることで、DXをよりスムーズに推進できます。
3-1. 経営層の課題
経営層は、DX推進のリーダーという重要な役割を担っています。しかし、DXに対する理解不足や短期的な視点での判断、現場への権限委譲の不足など、解決すべき課題も多いです。
たとえば、DXの重要性を理解していても、具体的な戦略やビジョンを明確に示せないケースがあります。これでは現場が混乱してしまうでしょう。
投資対効果を短期的に判断し、DXに必要な投資を抑制してしまうケースも少なくありません。現場に権限を委譲せず、意思決定が遅れてしまうケースも見られます。
【解決策】
経営層は、まずDXに対する理解を深めることが重要です。そのうえで、明確なビジョンと戦略を策定し、全社に共有する必要があります。DX推進のためのKPIを設定し、進捗状況を定期的に確認しましょう。こうしてPDCAサイクルを回し、継続的な改善を図る体制を構築できます。現場に権限を委譲し、迅速な意思決定を促すことも重要です。
3-2. IT部門の課題
IT部門はDX推進の要となる存在ですが、彼らは従来のシステム運用・保守業務に追われています。結果として、DX推進に十分なリソースを割けない、新しい技術への対応が遅れている、といった問題が起こります。
たとえば、既存システムの運用・保守に多くの時間を費やし、新たなシステム開発や導入に人材を割けない。クラウドやAIなどの最新技術に対応しきれず、DX推進の足かせになる可能性もあります。
【解決策】
IT部門は、従来の運用・保守業務を効率化し、DX推進に注力できる体制を構築する必要があります。外部のITベンダーを活用したり、クラウドサービスを導入するなどして、業務効率化を図りましょう。
最新技術に関する情報収集や研修などを積極的に行うことも大切です。常に新しい技術に対応できる体制を構築しておきましょう。
3-3. 現場の課題
ビジネスの現場となる各部署では、デジタル化に対する抵抗感やITリテラシーの不足、業務プロセス変更への不安など、さまざまな課題を抱えています。
たとえば、長年慣れ親しんだ業務プロセスが変わることへの抵抗感や、新しいシステムを使いこなせるかという不安から、DX推進に消極的な意見が出る場合があります。ITリテラシーが不足しているため、新しいシステムやツールを導入しても十分に活用できないこともあるでしょう。
【解決策】
現場の課題を解決するためには、DX推進の目的やメリットを丁寧に説明し、理解と協力を得ることが重要です。現場の不安を解消するためのサポート体制を整える必要があります。具体的には、ITリテラシー向上のための研修の実施、わかりやすいマニュアルの作成といった取り組みです。
【まとめ】自社の課題を明確にしたうえで、DX推進に取り組もう
DX推進はすべての企業にとって喫緊の課題であり、もはや避けて通ることはできません。しかしDXの推進には、人材不足やITリテラシーの不足、レガシーシステム、誤解、目的化など、さまざまな課題が存在します。
これらを克服し、DXを成功させるためには、まず自社の課題を明確に把握することが重要です。そして、経営層から現場まで、全社一丸となってDX推進に取り組む必要があります。
DX推進は、決して容易な道のりではありません。しかし、DXを推進することで、企業は新たな価値を創造し、競争力を強化できます。変化を恐れず、積極的にDXに取り組むことで、未来を切り拓いていきましょう。
DX推進において課題を克服し、成功へと導くには、専門的な知識とノウハウが必要です。当社では、DXコンサルティングサービスを通じて、企業のデジタル化を全面的にサポートいたします。DXにおける人材不足やITリテラシーの課題に対しても、的確なアプローチを提供し、貴社の競争力強化を支援します。まずは、貴社のDX推進に向けたご相談をお待ちしております。
▼▼▼お問い合わせは下記まで▼▼▼
https://www.kk-sun.co.jp/dx_support/
